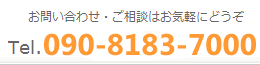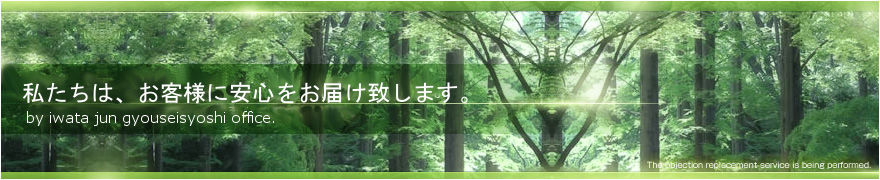労働者派遣事業
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。
労働者供給事業との関係
労働者派遣事業は、昭和61年の労働者派遣法の施行に伴い、改正される前の職業安定法第44条によって 労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、全面的に禁止されていた労働者供給事業の中から、 供給元と労働者との間に雇用関係があり、供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせないような形態を取り出し、 種々の規制の下に適法に行えることとしたものです。
一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類がありますが、その違いは主に以下のとおりです。
一般労働者派遣事業
いわゆる登録型の派遣であり、あらかじめ登録されている求職者とは、派遣先が見つかった時にだけ労働契約を締結して派遣する形態です。 常用雇用労働者の派遣も可能です。一般労働者派遣事業を行うためには、まず事業主単位(会社単位)で厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 (特定労働者派遣事業の場合は「届出」が必要です。) 常用雇用労働者以外の労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要となります。
許可にあたっては、財産基準や事業に使用し得る面積、必要人員の配置など、様々な要件があります。 また、許可後においても労務管理や、法改正への対応、許可の更新手続きなどの業務が必要となることから、 労働者派遣事業の運営に詳しい社会保険労務士と顧問契約をして、運営している事業主も少なくありません。
一般労働者派遣事業については、いわた行政書士事務所が担当させていただきます。
初回メール相談は無料です。安心してご相談下さい。
特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを派遣する形態です。派遣先との労働者派遣契約が終了しても労働契約が継続するため、その後に適当な派遣先がなく、 待機している場合であっても、その間の賃金(または休業手当)を支払わなければなりません。
特定労働者派遣事業を行うためには、事業主単位(会社単位)で厚生労働大臣に届出をしなければなりませんが、 一般労働者派遣事業のような財産要件や更新手続は必要ありません。
いわた行政書士事務所 活動エリア
愛川町 厚木 綾瀬 相模原 座間 町田 大和 横浜 サービスエリア圏外からのお客様も歓迎します。

|

|